お小遣い制で、長年タバコを吸っていた私の話をします。
他人から「やめたら?」と言われても反発したくなるのが人情ですが、もしその言葉が未来の自分からの手紙だったら――そう考えたとき、少しだけ態度が変わりました。
今回は「吸い続けた理由」「辞められたきっかけ」「辞めてから得たこと」を、同じ境遇の人に寄り添うつもりで書きます。禁煙を押し付けるつもりはありません。けれど「いつか変わりたい」と思う人の背中を押せれば嬉しいです。
私の喫煙年表と“やめられなかった理由”
学生時代からの習慣で、気づけば20年近くの喫煙生活。
一度は子どもが生まれたときに禁煙にチャレンジしたものの、3ヶ月で挫折。妻が病気になって受動喫煙の話を聞いても、自分ごとにはならず、さらに10年ほど吸い続けました。理由は単純で「若さゆえの楽観」と「ニコチンの依存」です。
喫煙スタイルも変わりました。値上げやiQOSの登場で銘柄を乗り換えつつ、日に2箱相当――感覚的には月2万円以上をタバコに費やしていたと思います。金額が大きくなるほど、やめどきの思考が揺れました。
なぜ“やめよう”と思えたのか —— 金銭面の決定打
健康や周囲の事情よりも、最終的に私の決断を動かしたのは「金銭面」でした。
たとえばセブンスターの価格が高騰して「1,000円で2箱が買えなくなる」危機を想像したとき、ふと「もう限界だ」と腹が決まりました。2018年9月、私は禁煙を開始。価格上昇のプレッシャーが“やめる理由”になったのです。
喫煙をめぐる“今”(社会的な変化)
2025年現在、飲食店や公共施設の禁煙化は当たり前に。吸える場所はどんどん縮小されています。
狭い分煙ブースでぎゅうぎゅうになって吸う光景を見ると、改めて「吸っているのは自分か、ニコチンに吸わされているのか」と考えさせられます。喫煙者の肩身は確実に狭くなってきています。
禁煙のデメリット(正直なところ)
- 喫煙仲間との交流が減る(社交の場が変わる)
- 思考作業が捗らない
- イライラがとまらない
- ストレスがかかる
- 死ぬまで、この禁煙の禁断症状が続くように思える
- 「やらない理由」を人は無数に見つけてしまう(禁煙が続かない言い訳が出てくる)
人間心理として、やめない理由はいくらでも見つかる――そこをどう乗り越えるかが鍵です。
禁煙のメリット(私が実感したこと)
- 喫煙できる場所に縛られない
社会の流れに合わせて、自分が“選ばれる側”にならなくて済む。 - 口臭・体臭・歯の見た目改善
見た目や臭いが改善され、家族や周囲の反応も変わる。 - 健康リスクの低下(中毒からの解放)
ニコチン依存から抜けることで病的な状態が緩和される可能性がある。 - 金銭的な余裕が生まれる(最も実感した点)
タバコ代を別の大切なことに回せる――ここに一番の価値を感じました。
金銭面の“具体的メリット”(私の場合)
禁煙で浮いたお金は、単なる節約以上の効果をもたらしました。
- ❶ お小遣い制度の改善に向けた“軍資金”確保
- ❷ 社員旅行や家族旅行など“体験への投資”が可能に
- ❸ 欲しいものを買える幅が広がる
- ❹ 本や自己啓発への投資がしやすくなる(学び→行動への好循環)
- ❺ 健康への自己投資(ジム・サプリ等)への心理的ハードルが下がる
- ❻ 友人との飲み会や昼食の出費にためらいが減る
禁煙は「節約」ではなく「投資余力を生む行為」だった――私はこう感じています。
読者へのメッセージ(未来の自分からの手紙として)
もし未来の自分(55歳・65歳の自分)から手紙が来て、「ありがとよ、あのとき決めてくれて」と書かれていたら――考え方が変わるかもしれません。もちろん、それでも変わらない人もいるでしょう。でも「変わりたい」と思う人には、まず“想像の力”が有効です。未来の自分が何を大切にしているかを想像することで、今日の選択が少し違って見えます。
まとめ(結び)
禁煙は人それぞれタイミングも方法も違います。私の場合は「金銭面の危機感」が決定打になりましたが、得られたものはそれだけではなく「選択肢の広がり」や「心の余裕」でした。もし今、やめたい気持ちと反発が戦っているなら、未来の自分に手紙を書く――そんな小さなワークから始めてみてください。変化は小さくても、長い目で見れば大きな差になります。
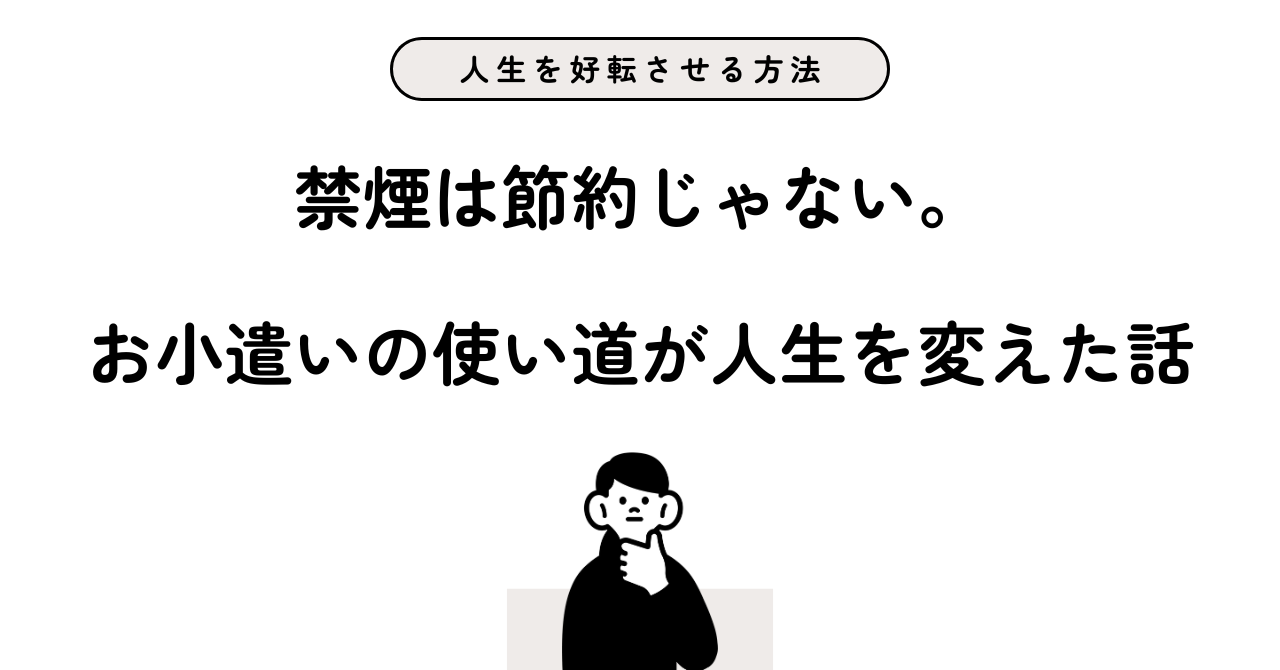
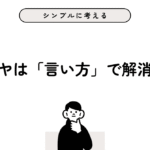
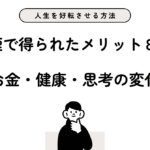
コメント